大手ERPベンダーのWorkday(ワークデイ)が、AIによる企業変革の新たな段階を予感させる数々の発表を行った。本稿では、同社が2025年9月に米サンフランシスコで開催した「Workday Rising 2025(以下、Rising)」の期間中に行われた、APAC Japan地域の報道陣とのグループインタビューの内容をお届けする。インタビューに応えたのは、同社の営業やマーケティングなどを統括するロブ・エンスリン氏と、製品・技術全体を統括するゲリット・カズマイヤー氏だ。ビジネスとテクノロジーの両面から、人事・財務領域を中心にオープンプラットフォームを提供する同社がAI時代に重んじる思想と戦略、さらには今回のRisingで掲げられたERPの再定義を意味する「Next-Generation ERP(次世代ERP)」の意図などを解説いただいた。
AIは仕事を奪う?それとも「さらなる雇用」をもたらす?
ロブ・エンスリン(Rob Enslin)氏は、2024年11月にWorkdayに参画した。SAPでの27年間のキャリアを持ち、2005年~2008年には日本法人の社長も務めたほか、Google CloudやUiPathの経営にも関わった経験を持つ人物だ。
![ロブ・エンスリン(Rob Enslin)氏[President & Chief Commercial Officer, Workday]](https://ez-cdn.shoeisha.jp/static/images/article/23247/23247-1.jpg)
ロブ・エンスリン(Rob Enslin)氏
[President & Chief Commercial Officer, Workday]
最初に他国の記者から出た質問は、「AIが人の仕事を奪うのではないか」という懸念についてだった。Workdayがプラットフォームを提供する財務・人事領域でも囁かれている問題だ。エンスリン氏は、「もちろん、AIプロダクトを提供するすべての企業はこの議論に対処しなければならない」と前置きしつつも、市場にある誤解を指摘した。
「従業員削減が世界中で加速するなどといった主張が混乱を招いています。IT業界の中にも、『もう以前のような多くのスタッフは必要ない』『従業員を減らせる』などと謳っている企業がいますが、これはナンセンスです」(エンスリン氏)
Workdayは、約2年前から「AI Everywhere」というアプローチを社内で採用している。各部門は希望するAIを導入できるが、効率性と企業価値の向上に焦点を当てることを条件として課す仕組みだ。管理体制の下で、どのAIプロジェクトが成功しているのか、あるいは成功しそうか。また、停止すべきプロジェクトはあるかを測定している。
たとえばAI導入プロジェクトの一例として、約4,000人のエンジニアがコーディング支援ツール「Cursor」を使用し、25〜30%の生産性向上を実現した。「エンジニアたちは、コーディングの中の退屈な作業をする必要がなくなり、より幸せな働き方ができるようになった」と、同氏はAI導入で得られた効果を語る。
業務が削減・効率化されたことで、従業員は解雇されるどころか、むしろさらに必要となった。エンジニアに関しては、従来と同じ時間でより多くのプロダクトを生み出せるようになり、市場に出す(≒収益につながる)スピードも加速しているため、より多くのエンジニアが必要になっているのだという。この例では、AIは雇用を奪うのではなく、企業の価値を高めることで結果的により多くの雇用を生み出しているといえる。
カスタマーサポートのチーム内でも変化が起こった。検索とインデックス機能を活用し、顧客からの問い合わせをデータベースに直接接続して即座に回答を提供することで、効率レベルが劇的に向上したという。
効率化がさらなる仕事をもたらす一方、エンスリン氏は労働人口が減り続ける地域でのAI活用の重要性も語った。日本はその最たる例といえる。同氏は、「日本は特に人口動態の縮小が顕著な国の一つだが、AIは未来を変えてくれるだろう。少ない労働人口でも、より高い生産性を実現できるからだ」と説明。加えて、AIと人間の関係性については、「AIが人間を駆り立てるのではなく、『人間がAIを駆り立てる』という方向性がより優位になると強く確信している」とも述べた。
そんなWorkdayの新たなAIやソリューションは、日本ではいつ利用可能となるのか。今回のRisingでは、人事・財務や業種の課題に特化した新たなロールベースのエージェンティックAIをはじめ、数々の新ソリューションが発表された。
日本でのWorkdayは、特にHCM(人的資本管理)のニーズを背景として大きくシェアを伸ばしている。今回発表されたエージェント関連機能のローカライゼーションについては、Tier1地域では2026年中に即座に利用可能になる予定だ。「日本もTier1地域として、優先リストの最初に入っている」とエンスリン氏は明かした。
Sana買収で実現する“自然言語時代”の「民主化された企業システム」とは?
Workdayは今回のRisingでSana Labs(以下、Sana)の買収を正式に発表した。エンスリン氏はこれについて、「私のキャリアで最もエキサイティングな買収だ」と語る。AIネイティブな学習プラットフォームを提供する同社の買収により、ナレッジワーク領域でのテクノロジーの民主化を目指すとしている。

1990年代から2010年代までに構築されたシステムのほとんどは、特定の職種や立場の人にしかわからない、いわゆる“専門ユーザー向け”に設計されていたとエンスリン氏。企業の上級管理職は、現場の従業員が使っているプラットフォームにはほとんどアクセスしないし、使い方や見方もよくわからない。あるいは、まったくアクセスせずスタッフにレポートを依頼している場合もある。
しかし、SanaのテクノロジーがWorkdayプラットフォームに統合されることで、立場や専門性を問わず自然言語での対話と検索が可能となる。「今日のコストセンター構造を教えて」「このまま運営を続けると3ヵ月後に予算は超過しそうか?」といった質問を自然言語で行い、システムが自然言語で回答するのだ。

Sanaは自社のプラットフォームを「エンタープライズリサーチツール」と謳っているが、その特徴は大きく2つある。1つ目は「ノーコード・エージェントビルダー(No-Code Agent Builder)」だ。ユーザーが「このデータをもとにこんな作業ができるエージェントが欲しい」とシステムに伝えるだけで、コードを見ることなくエージェントを構築してくれるのだという。このビルダーはSlack、Teams、Docsなどにアクセスし、必要なデータを取得できる。
2つ目の特徴は「学習体験の向上」だ。多くの会社が、自社内に従業員向けの学習コンテンツやカリキュラムを備えているが、従来の学習教材は急速に陳腐化し、かつ高コストで作成には時間がかかるという問題が顕在化していた。しかしSanaでは、「AIをもっと活用したい。プロンプトの作成方法を教えて」とシステムに依頼すれば、動画、音声、PowerPointなど希望する媒体で、自動的に指導内容とコースを作成してくれる。個別最適化された多様なメディアによる学習体験により、従業員は必要な時に必要なスキルを習得できるようになるというわけだ。
「真の価値を持つエージェント」の条件とは何か
AIエージェントの進化については、エンスリン氏は現実的な見解を示した。
「“自律型AI”とはいいますが、AIエージェントが朝起きて『何をしようか』と自発的に行動することはありません。エージェントは人間と同じように管理される必要があります。市場では完全自律の『スーパーエージェント』が話題になっていますが、完全にナンセンスです。現在の技術では、AIが自らビジネスプロセス全体を理解し、AIエージェントだけでそれを再構築することは不可能です」(エンスリン氏)
同氏は、真の価値を持つエージェントの条件として、「TCO(総所有コスト)の効率化」と「顧客への完全な透明性」を挙げた。Workdayもその考え方に基づき、「フレックスクレジット(Flex Credits)」モデルでAIを提供している。これは、AIのためのプレミアムライセンスとは異なり、すべてのAI機能を単一の使用量ベースで提供するという料金体系だ。
このモデルなら、ベースのサブスクリプションに既にクレジットが含まれているため、新しいエージェントがリリースされても追加契約は不要だ。使用量が増えた場合は、ユーザーの判断で追加購入するか、それとも他の機能を停止して総コストを抑えながら調整するかを選択できる。「エージェントが生み出す価値を示し、顧客が使用するかどうかを自身で決定できるモデルだ」と同氏は説明する。
EnterpriseZine読者に送るWorkdayの魅力
EnterpriseZineの読者の多くを占めるITリーダーに向けては、Workdayのプラットフォームの魅力をどう伝えるべきか。人事や財務に携わる方であれば、Workdayのプラットフォームで実現できる組織や人材、財務の変革を知ればその良さをすぐに理解できるかもしれない。しかし、IT部門にとってのWorkdayの魅力とはいったい何なのか。
エンスリン氏は、「Workdayの真の強みは、人事、財務、ITの間に従来からあった『壁』を大きく取り払う点にある」と述べる。人材、財務、プランニング(Adaptive Planning)を単一のプラットフォーム上で統合することで、IT部門は複数のバラバラなシステムを管理する必要がなくなり、日々のメンテナンスに囚われるのではなく、イノベーションの推進に注力できるようになるのだという。
「この統合プラットフォームによって、ビジネスリーダーはより迅速かつ質の高い意思決定を行えるようになります。従業員と財務の状況をリアルタイムで把握し、マニュアルな作業をなくす自動化と、組織の変化に柔軟に対応できる適応力が得られるのです」(エンスリン氏)
さらに同氏がアピールしたのは、Workdayのプラットフォームが持つオープン性と高い拡張性だ。これにより、強固なガバナンスとセキュリティを維持しながらも、既存のシステムやツールと簡単にプラットフォームを連携できる。
ここまでを踏まえ、同氏はEnterpriseZineの読者に向けて、「皆さんの日々の仕事を楽にするだけでなく、複雑性を解消し、将来のイノベーションのための土台を提供するのがWorkdayだ。その結果として、人事や財務に携わる方がビジネスに対してより大きな成果を出せるようになる」とメッセージを送った。
エンタープライズAIに必要な「安全性」の問題にはどう応える?
同日中に、同社で技術戦略を統括するゲリット・カズマイヤー(Gerrit Kazmaier)氏にも話を伺う機会があった。同氏もまたSAPでの経歴を持ち、そこではデータベース、データ管理、アナリティクス分野のプロダクトエンジニアリング責任者を務めていた。その後、Googleでも同様の分野で責任者を務めた。
![ゲリット・カズマイヤー(Gerrit Kazmaier)氏[President, Product and Technology, Workday]](https://ez-cdn.shoeisha.jp/static/images/article/23247/23247-2.png)
[President, Product and Technology, Workday]
同氏はまず、AI技術の安全性について、Workdayの中に存在する厳格な仕組みを強調する。同社内には「AIガバナンス委員会」が設置されており、安全なAIエンジニアリング手法を実践する組織体制を整えている。
AIバイアス対策では、3段階のアプローチを採用しているという。トレーニングデータの①バイアス軽減技術、②属性情報の完全分離、③テナント分離モデルだ。
「性別や民族など、バイアスを引き起こす典型的な要素がありますね。私たちのAIモデルは、これらの属性を一切考慮しません(属性による判断や生成結果への影響は一切ないという意味)。モデルのトレーニングは、顧客テナント内のモデルに対してのみ行っています。これらは共有されず、外部モデルプロバイダーにデータをアップストリームすることは一切ありません。このアプローチにより、セキュリティ向上はもちろんのこと、顧客間のデータ混合による統計的なバイアスも発生しません」(カズマイヤー氏)
実際、Workdayのテナントと顧客データを侵害するようなインシデントはまだ発生していない。国際標準への対応も迅速で、AIマネジメントシステムに関する国際規格 ISO 42001についても、標準公開から数日以内にASEAN地域での準拠を達成した。
エージェントの管理については、Workdayは「人間と同じレベルでエージェントを管理する」アプローチを採用している。同氏は、ほとんどのAIが組織で“技術資産(IT資産)”として管理されている現状に言及し、「AIエージェントがより自律的になるにつれて、従業員と同じセキュリティモデルが必要になっていくだろう」と警鐘を鳴らした。
Workdayの場合、たとえばMicrosoft Entra IDとの統合では、エージェントの署名もWorkdayプラットフォーム内に登録され、アクティブとして認識される仕組みを実現した。エージェントの展開文脈により、精度向上とセキュリティ強化を両立させている形だ。
ベンダーオープン性については、AIをエコシステムと捉えることが重要だと同氏。「多くの企業が、AIで良い結果を出すのに苦労している。その理由の1つに、誰もがAIインフラの周りに壁に囲まれた庭を作っているからだ」と指摘する。
Workdayは、MCP(Model Context Protocol:AIエージェント間の相互運用プロトコル)のような標準だけでなく、データ、ビジネスプロセス、他のエージェント呼び出しができるプラットフォームを設計している。今回のRisingでは、Snowflake、Databricks、Salesforce、MicrosoftのプラットフォームとWorkdayがシームレスに接続可能になることが発表された。プラットフォーム間で、データをゼロコピーで連携できるようになる。
なぜ「次世代ERP」の構想を掲げたのか、システムの概念を再定義する
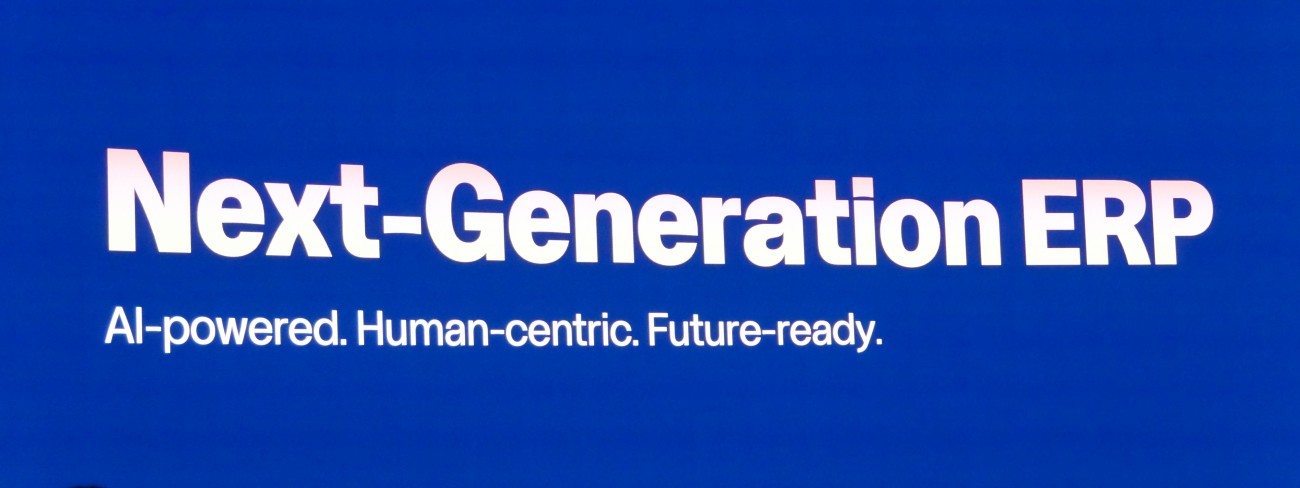
今回のRisingで注目を集めたのが、同社が打ち出した「Next-Generation ERP(次世代ERP)」という概念だ。従来のERPにはどのような課題があったのだろうか。カズマイヤー氏は次のように説明した。
「企業の情報管理の在り方はとてもカオスで、標準ビジネスプロセスも、真のシステム・オブ・レコード(System of Record)もありませんでした。従来のERPは、すべての機能が静的なコードであり、機能を拡張する際の柔軟性に欠けていたのです」(カズマイヤー氏)
しかし、ビジネス環境の変化がスピードアップするにつれ、事業計画は年1回ではなく、毎週のように見直される必要性が出てきた。同社が提供する「次世代ERP」は、この課題への回答になるという。実現するのは、AIの介在による柔軟性の向上だ。「AIは、ERPのすべての機能要素を分解できる。静的コードを分解し、動的な方法でAIインテリジェンスが機能を駆動する」と同氏は語る。
ユーザー体験も向上する。ERPは、適切な情報を提供し、AIインテリジェンスでアクションを実行するワークキャンバスのようなものになるという。
具体的な取り組みとして、Workdayは人事(HR)領域における採用プロセスの完全AI化を目指している。CRMからタレントプールの構築・管理、エンゲージメント、採用、面接プロセス、オンボーディングに至るまで、AIエージェントとの協働を通じて実現する世界だ。リクルーターは管理作業にリソースを割く必要はなく、従業員や候補者とのエンゲージメントに集中できるようになる。
他にも財務分野では、ドキュメントインテリジェンスを活用し、ドキュメントが作成または読み取られる財務フローの全工程にAIを適用し、プロセスを完全に自動化する取り組みを推進中だ。
カズマイヤー氏は、AI技術がさらに浸透した世界でのビジネス変革を予測する。
「AIが次世代ERPの中で機能するようになれば、企業そのものの在り方を変えることができます。労働力とは何か、プロセスとは何かを再定義し、顧客とのエンゲージメント方法、サプライヤーの管理方法、さらにはすべての従業員の働き方について、組織全体の考え方や価値観を変えることができるのです」(カズマイヤー氏)
もちろん、この変革はすぐに訪れるものではなく、実現には時間がかかる。こうしたサイクルは年単位で測定される。「ほとんどの企業でAIベストプラクティスが広く採用されるまでには、まだ何年も要するだろう」とカズマイヤー氏は現実的な見通しを付け加えた。
単なる静的なシステムではない、「オープンなシステム」であることがWorkdayの真価
EnterpriseZine(聞:名須川)は、日本企業に蔓延っているIT部門と他部門の分断についてカズマイヤー氏に尋ねた。ここでの「分断」とは、Workdayプラットフォームの主なユーザー層である人事・財務部門と、システムの構築・運用を担うIT部門の間で起こるコミュニケーションの分断や、それが原因となって発生する目的・課題意識のギャップ、ITプロジェクトの難航、現場で使われない(or 使いにくい)システムやアプリケーションの量産などといった問題を指す。エンスリン氏に最後に投げかけた質問と似ている内容だが、カズマイヤー氏にも尋ねてみた。
同氏は、「そうした問題こそが、Workdayがオープンプラットフォーム戦略を打ち出す理由だ」と説明した。
同社のプラットフォームは、特定の専任部署やエンジニアだけが使うのではなく、全社員が立場や部門を問わず社内でアクセスし、利用し、カスタマイズできる設計になっている。たとえば人事システムであれば、中央の人事部だけがアクセスして使う単なる管理システムではなく、従業員一人ひとりが自由にアクセスし、自身のキャリア設計や人事部とのプラットフォームを通じた双方向でのコミュニケーションなどに活用できるハブのような世界観になっている。
こうしたオープンなシステムは、日本の伝統企業や大企業に所属する人事・財務領域の方にはあまり馴染みのない体験かもしれない。しかし、ITに携わるEnterpriseZineの読者にとっては、その良さが理解しやすいはずだ。
「IT部門の人たちなら、オープンな世界には既に馴染みがあるでしょう。皆さんはいつでもオープン標準、オープンAPI、オープンプログラミング言語を求めます。複雑なシステムを運営するIT組織は、新しいものを導入する際、他の既存要素とどうそれを適合させるかを理解する必要があるからです。Workdayのプラットフォームは、その価値観を人事や財務、さらには組織全体に適用させるものだといえば伝わるでしょうか」(カズマイヤー氏)
今回のRisingで発表されたオープンプラットフォーム戦略や、AI開発プラットフォームの「Workday Build」、データ統合基盤の「Workday Data Cloud」、そして新しいエージェント群は、CIOが既存・新規問わずシステムを統合し、その上でイノベーションを推進できるように設計されているという。
同氏は最後に、Workdayは単に製品を提供するだけのベンダーになるのではなく、変革のパートナーとしてユーザーにもWorkdayに伴走してほしいという想いを語った。
「世界中のユーザーが、Workdayのベストプラクティスを活用した変革支援を求めています。そのプラクティスを、我々全員で共創していきましょう。そして、そこで得られたフィードバックや発見が、Workdayのソリューションをさらに良いものへと進化させるのです」(カズマイヤー氏)
Enjoyed this article? Sign up for our newsletter to receive regular insights and stay connected.

